【コメンテータより】
●学問を「答える学問/問う学問」に大別すると、いま前者が強い傾向がある。たとえば環境社会学(とくに原発研究)では、すぐに賛否や政策提言を求められてしまう。
●「問い-答える」という人間の根本的な営みが重要であり、かつ深く上手に問うことが必要である。その際、フィールドの人の方が切実な立場にあって自分よりもよく考えているということに気付き、それらを手がかりに自分の問いを鍛えていきたいと考えている。
●生き方としての学問である。学生の調査教育などで「問う」ことが欠落してしまうと、「畳の上の水練」同然となってしまう。問いを残し、積み重ねていかないといけない。
【自由質疑/討論】
●そこで、全員への質問になるが、現場の切実な問いを感じた例はあるか。また、現場の問いと研究の理論的テーマとのつながりは何か。
○少数言語をめぐる切実な課題はいつも感じているが、「異なるふたつの言語集団がある」というにとどまらない、非対称な関係がある。マジョリティ聴者はろう者のことを忘れてふるまうことができるが、マイノリティろう者は聴者のことを忘れてふるまうことができず、職場でも家庭でも常に「ことばの通じない多数派」のことを勘案しながら行動することを余儀なくされる。国民や市民、地域住民などの帰属よりもまず「手話を話すわれわれ」を立て、音声言語集団との距離の取り方を考えるという傾向を感じる。その距離の取り方は地域や集団によりさまざま。
よって、私の理論的関心としては、ろう者社会と聴者社会との距離の取り方の多様性がある。アフリカのように独立性が高いが干渉もないあり方、逆に日本のように聴者からの干渉の強いあり方など。広くデータを集めて比較してみたい。その理論的なテーマの追究が、ろう者たちが現場で切実に感じている多くの課題、ろう教育、通訳者育成、手話普及、一般啓発などの問題に対処するいとぐちとなることを期待したい。
○過疎化、少子高齢化と単純な問題設定をしたのは軽率だった。この裏にある様々な問題を紐解いていく作業が必要で、その方法のひとつがフィールドワークなのかなと思う。例えば、この「化」のスピードや条件は地域によって異なるのに、どこもこぞってグリーンツーリズムや人口増加対策等の一律的な傾向に陥っている現状。本当にそれでよいのか。そう思っていても、一生懸命、それらに取り組んでいる住民にはなかなか言えない…。そんなとき、ある人が、「過疎って悪いことですか?」という問いを発した。おそらく、その言葉が、集落をどう閉じていくのか、閉じ方を、住民だけでなくよそ者も、本気で考える契機になったように思う。
[理論的テーマとのつながりは、セッションでは、お答えできなかったので、人類学とはちょっとずれるかもしれないが、追加する]かつて、農村社会学において、戦後、むらを近代化の阻害要因「封建遺制」として捉えた共同体論の後、1970年代に、共同体的機能を集落自治の基盤として見直す「むら再評価論」が登場し、そして、理念型的二項対立のなかの円環運動から抜け出ていないといわれていた。これらは過去の議論であり、今は下火になってしまったような感があるが、私は、この過程を踏まえたうえで、現在のむらをどう位置づけるのか、どう捉えるのか、ということを検討していきたいと思っている。さらに、「共同体論」として理論的に確立しているが、「むら再評価論」は現場重視で、イデオロギー的な運動論で終わっているともいわれているので、ここにも、アクションと研究の狭間における研究者の格闘が存在しているような気がしている。
○「動くべきだ」というのではなく、「動けた方がいいだろう」というのが私の認識で、他の場所でもそうした理解をされたのだが、「動きながら考える」の「考える」には、理解が含まれている。ところが、臨床の場合、問題を抱えている当事者がある種の情報を意図的に隠していたり、話されなかったりする事があるので、「動く」ことでけしかけることもある。けれどもそう考えれば、人類学のフィールドワークでも同じようなものがあり、何年かフィールドに通って初めて分かることもある。なので、両者の距離は想定されがちなものよりも、実際には近いと考えている。
文化人類学会ではコメンテータから、アクションから学問への還流の重要性(「研究に資するアクション」)についての指摘があった。けれども逆に、学問からアクションへの還流(「動きに資する研究」)はないのですか?と問うてもいいと思う。
●今日の発表は、(辰己さんの発表はちょっと違ったが)みな従来型の native's point of view の話ではないか。それを超えようとするセッションの全体趣旨は反映されているのか。また、現地調査において native の言語を用いるべきだという議論は、以前からなされているはずである。
○from the native's point of view を否定したつもりはない。ただ、それはホームで論文を書く際の役割分担のあり方であって、フィールドでは全人格的に巻き込まれることがある。そんなときに、あれこれのアクションを迫られることがあり(e.g.ピナトゥボ火山の噴火の時に清水展さんは「調査」はしなかった)、ホームに戻ってきてからの「理論人類学」とか「実践人類学」とかの両極での立ち位置を意識する前に、フィールドでの状況と、そのアクションの知恵を集めようというのが趣旨。なので、from the native's point of view はあっていい。ただ「それだけ」でやろうとしなくてもいいだろうということ。そうすれば人類学はもっと豊かな学問になれると思っている。
○手話をめぐる研究の取り組みについては、まずもって研究者らが native's point of view の認識のレベルに達することが必要であるという現状がある。また、音声言語マイノリティの場合は、マジョリティ言語(英語など)を用いて声をあげることもできるが、ろう者の場合は身体的に大言語への同化が困難な人びとであり、たとえばマイノリティとマジョリティのそれぞれのあり方について対話しようにも、まず手話通訳が必要であり、手話が共通言語とならざるを得ない。そのふたつの意味で、手話の使用をとくに強調する必要がある。
●理解から実践へと振れた70-80年代の議論があった。それは重要だし、あってよい。ただ、それぞれの課題の速度や緊急度が違うので、それぞれなりの戦略が必要。一緒くたに語るのはまずいのではないか。
●媒介者としてのフィールドワーカーであるならば、そこをアクションと呼ぶという理解でよいか。理解するだけでなく一緒に行動するという意味か。
○[質疑の際には上手く理解し得なかったので、ここでは応答を補う]最高峰の人と最底辺の両方に渡りをつけられるのは人類学者である。一種のリソースである。「行動」にもいろいろあるので、Aさんに「Bさんがこんなこと言ってましたよ」と伝えて関係を良くするのもアクションになるだろうから、この質問で想定されているであろう、「行動」に当てはまらないような世間話も「アクション」には入ると思う。
●自分のたずさわる呪術研究と、ここで論じられているアクションは、どうもそぐわない。呪術の前においてフィールドワーカーは圧倒的に無力である。アクション論は、自己決定・自己責任に代表されるようなネオリベ的な主体とどう違うのか。
○ネオリベなどの問題設定以前に「すでに動いている私たちがいる」という認識に立って本を編んだ。
○新しいアクションを一個ずつ付け加えていこう、というよりも、「すでに手を染めているのだからそれを直視しましょう」という視角の提案。こうすべきだ、というよりも、これまでどんなことをしてきましたか?という問いを発し続け、アクションの収集をしていきたい。
●アクションとは能動的なものか受動的なものか。
○状況にまきこまれながら行われることもあるため、二分できない。なお、フィールドワーカーが超越的な主体としてアクションの自己決定権を独占しているのではないことだけは確かである。
●人類学者は非常に非力な存在である。現地でのアクションや実践を叫ぶのは自意識過剰ではないか。
○確かに、開発プロジェクトなどの方が、現実を大きく変える力を持っている。しかし、人類学者はさまざまな立場の人に直接アプローチする(行き来する)能力を持っており、それが寄与する面は大きいはずである。
●アクションというのは、ことさらに言わなくても、誰もがやっていることではないのか。
○それが酒場の会話や裏話になっていて、その知恵を集めてみることで学びあおうというのが本来の趣旨(論文ではその部分は現れてこないので)。
●あれでは運動家と変わりがなくなってしまうのではないか。学問は現地に寄り添う点では運動家のようにはできないのだから、むしろそこから引いて相対化するのが学問的な真摯さではないか。
○まずは「そうしなければならない」と言っている訳ではない。その上で、「運動家と変わりがなくなってしまう」という場合、「運動」と「学問」が別のものとして想定されているようではあるけれども、臨床心理学や社会工学などは、働きかけることの論文化が学問になるので、運動と学問が別にならない領域がある。また、「運動」家のようにやれなければ「学問」的になると設定すると、いかにも相互排他的な考えになってしまうけれど、その間に立つ存在がいることによって、フィールドで、運動家には支援できない領域に、そうしたアクションが相手の選択肢を多数・多様化する余地があると考えているので、AでなければB(のはず)だ、と考えることはないと思っているし、それは独自の意味をもつ領域だと思っている。
●今回の発表は研究者にむかってのものであり、論文というのはまずもって研究者内での評価を求めるものだろう。その人たちに向かってアクションを呼びかけるのは、いったいどういう意味があるのか。
○臨床心理学や社会工学などのような学問領域の場合、学会内での論文の評価は、そこが最終目的になるわけではなく、学会の査読等は社会に働きかけるそのやり方のチェック機構としての意味を持つ。その場合、論文化を通じて、そのアクションが社会に戻ってゆくので、そこでの働きかけが目的となる。そうした領域を開いてもよかろうというのが趣旨で、その場合、「こういうアクションがある」というのを共有しておくと、フィールドワーカーの現場での動きも豊かになると思っている。
□セッションを終えて(コーディネータ: 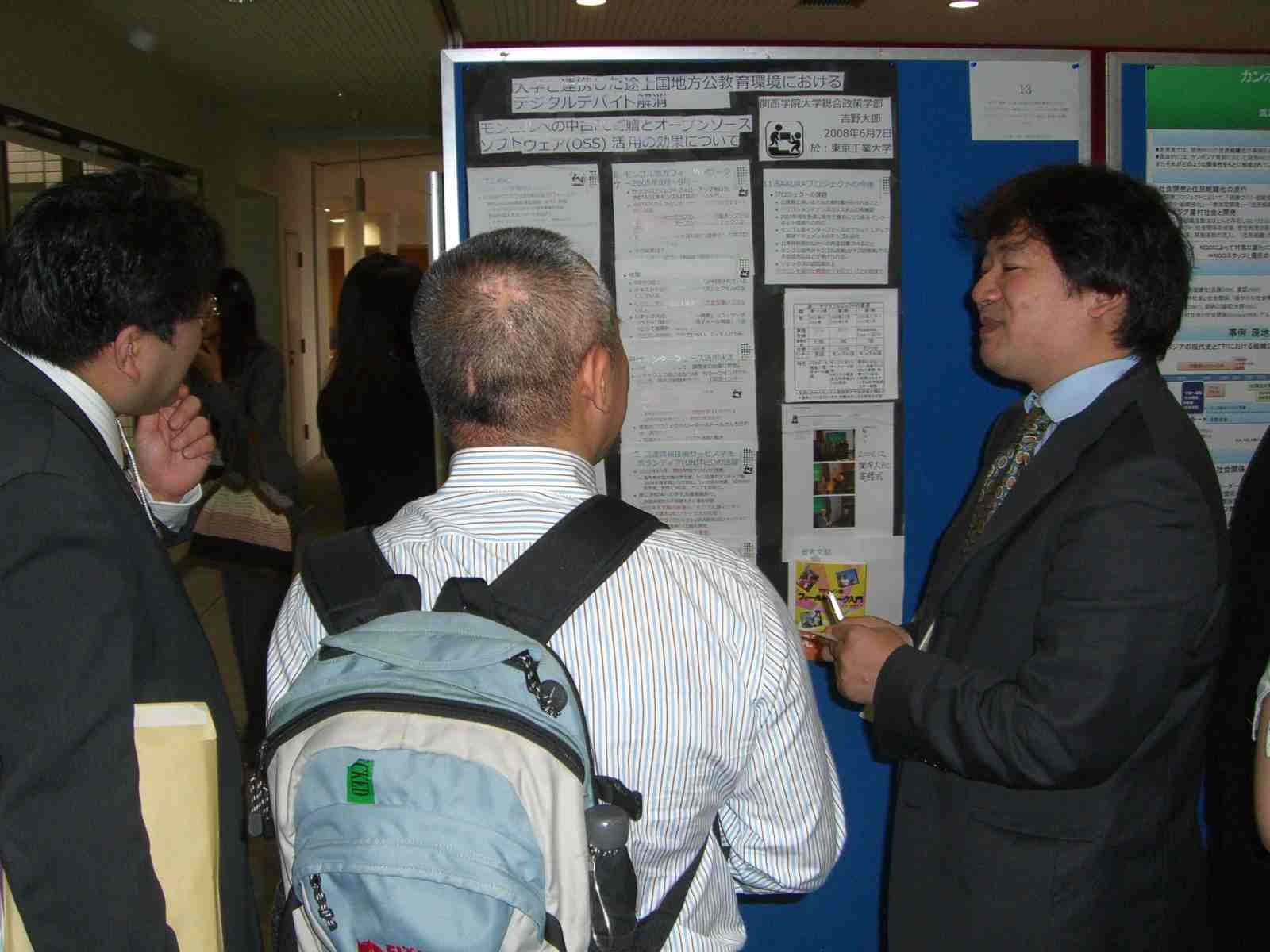


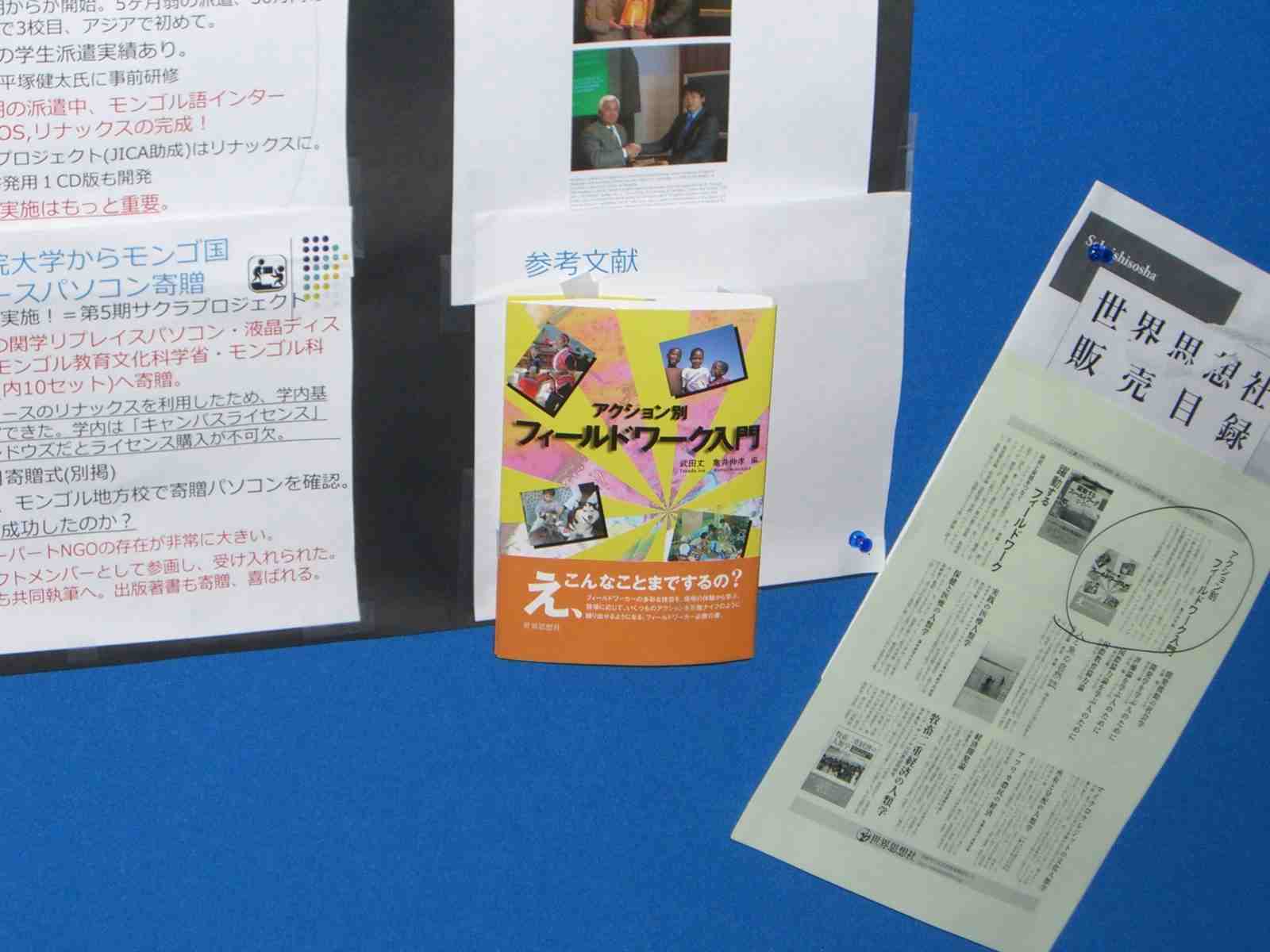



 このページのトップへ
このページのトップへ 『アクション別フィールドワーク入門』トップへ
『アクション別フィールドワーク入門』トップへ